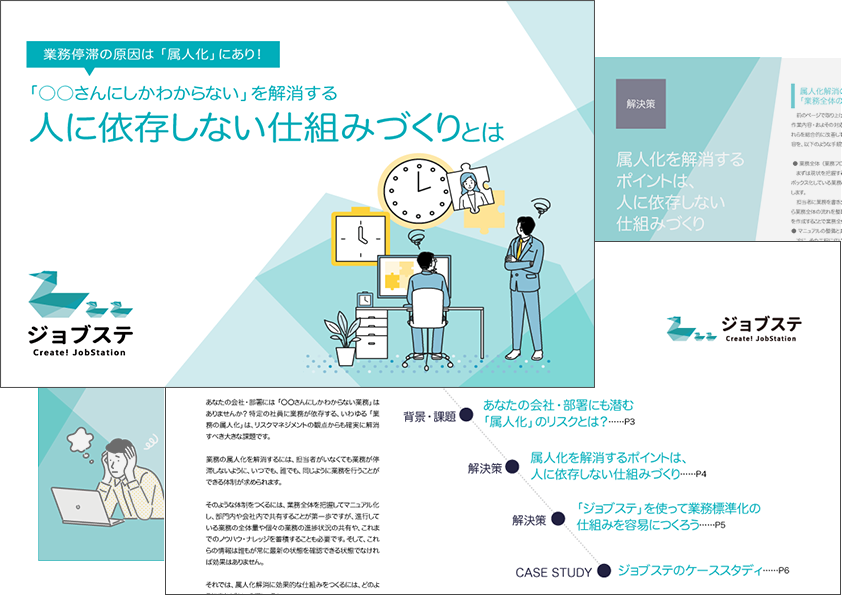
▼ダウンロード資料を途中まで読む
あなたの会社・部署には「〇〇さんにしかわからない業務」はありませんか?
特定の社員に業務が依存する、いわゆる「業務の属人化」はリスクマネジメントの観点からも確実に解消すべき大きな課題です。
業務の属人化を解消するには、担当者がいなくても業務が停滞しないように、いつでも、誰でも、同じように業務を行うことができる体制が求められます。
そのような体制をつくるには、業務全体を把握してマニュアル化し、部門内や会社内で共有することが第一歩ですが、進行している業務の全体量や個々の業務の進捗状況の共有や、これまでのノウハウ・ナレッジを蓄積することも必要です。
そして、これらの情報は誰もが常に最新の状態を確認できる状態でなければ効果はありません。それでは、属人化解消に効果的な仕組みをつくるには、どのようにすればよいのでしょうか。
属人化解消のためのホワイトペーパー
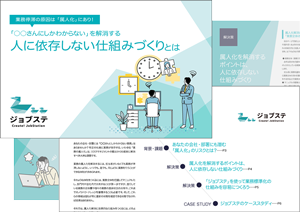
こんな人におススメ
- 属人化を防ぐ体制づくりを知りたい
- 属人化解消に取り組みたい
- 属人化を解消するのに何から取り組めば良いかわからない
目次
- あなたの会社・部署にも潜む属人化解消とは?
- 属人化解消するポイントは、人に依存しない仕組みづくり
- 「ジョブステ」を使って業務標準化の仕組みを容易につくろう
- ジョブステのケーススタディ
あなたの会社・部署にも潜む属人化解消とは?
担当者への依存が招く、様々な問題
どの会社・部署でも、てきぱきと仕事をこなしていく社員は重宝されているでしょう。
しかし、「気が付いたら業務の流れや進捗が担当者にしかわからない」という状態に陥ることがあります。このような状態は総務・人事・経理などのバックオフィス業務や定型業務にも多く見られ、「属人化」というキーワードで、たびたび業務上のリスクとして取り上げられています。
それでは具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。
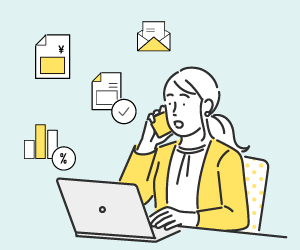
まず、属人化している業務では、作業の進め方やどこまで進んでいるかについて特定の担当者しか情報を保持していません。 そのため、担当者が出張や休暇などの理由で不在になると一時的に業務が停滞してしまいます。
さらに、担当者の異動や退職に至っては、引き継ぎが難航することや、細かなナレッジやノウハウの共有までは行き届かないことから、業務効率や品質の低下が生じます。 また、特定の担当者だけに作業が集中することは、業務遅滞や 慢性的な超過労働・他の業務担当者との労働時間の差が生じてしまう懸念があり、労務管理の問題に発展することも起こりえます。
どのような事情があっても、業務の作業手順や進捗状況といった情報を特定の個人に保有させることは、周囲や部門間もしくは全社での情報の共有や伝達不足につながり、様々な問題を引き起こします。
このような業務の属人化のリスクは、程度の差こそあれ、どの会社・部署にも潜んでいるものです。
属人化解消のためのホワイトペーパー
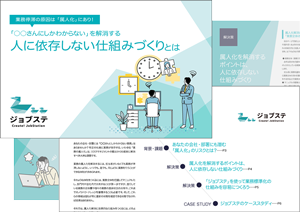
こんな人におススメ
- 属人化を防ぐ体制づくりを知りたい
- 属人化解消に取り組みたい
- 属人化を解消するのに何から取り組めば良いかわからない
業務の属人化はなぜ起こるのか
業務の属人化が起こるのには、様々な理由が考えられます。最近では、人員不足の影響からバックオフィスの仕事を少ない人数で回しているうちに、担当者が次第に固定化して業務が属人的になってしまうことがあります。 このようなケースでは個々の社員の業務範囲が広かったり、仕事量が多い傾向にあったりするため、周囲と情報やノウハウを共有したくても共有する相手や環境がなく、忙しさに追われて情報共有が後回しになってしまいます。
情報共有の必要性を担当者自身が理解しながらも手立てを検討できないような状態では、問題が起きていなくても、属人化している可能性が大いにあります。
また、業務の作業手順を定めたマニュアルを用意しているにもか かわらず、社内や部署内の誰もが閲覧できるように管理・共有されていない場合も、業務が属人化しやすい環境です。
- 「業務マニュアル がどこにあるのかわからない」
- 「作業手順が変わってもマニュアルが 更新されていない」
- 「イレギュラーな処理があっても現在の担当者し かわからない」
このような状況ならすでに業務の属人化が進んでいると言 えるでしょう。

さらに、意外な理由として挙げられるのが「豊富な経験をもった優秀な社員」の存在です。そうした社員は、自分の仕事を早く正確にこなせますが、そのスキルは当人の中だけに"ブラックボックス化"していることが多いです。
周囲はそれに気づくこともなく、いつしか「その社員に任せておけば安心」という雰囲気が生まれ、気が付くと業務が属人化してしまいます。
このような業務の属人化は会社や部署にとって見過ごすことができない問題ですが、単に担当者を増員すれば解決するものではありません。
では、業務の属人化はどのように解消していけばよいのでしょうか。
●続きは資料をダウンロードしてお読みください
必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください。
お客様からお預かりした情報をもとに、担当より日時確認のご連絡を差し上げます。
